住宅デザイン特集
「階段」を薄暗く湿った移動用空間にしないことは、住宅デザインにおいて大事です。階段に設けられる「窓」は、設計上、付けられる位置や高さが限定されてきます。その制限の中で、隣の家の窓の位置や、景色を眺める最善の位置を微調整し、階段照明等とのバランスで決められています。





蹴込み板を無くして、サイドパネルもスケルトン、大きな窓を付けて、明るい空間に。デザイン性の優れた空間となりました。小さなお子様がいらっしゃる場合は少し難しい、大人の空間デザインです。





黒の空間。ほぼ黒に近いブラウンの木目調で、壁は真っ白。階段空間と居室を半透明の開閉壁で仕切って、採光を確保しながら冷暖房効率を上げています。階段照明のスイッチも黒と、徹底した統一感。ちなみにですが、エアコンも黒です。



白の空間。階段に小窓を付けて採光通風を確保。小さな窓でもFIX窓(はめごろし)にせず、開閉できるようにしています。廊下にも小窓が付いていて、風が吹き抜けます。適切に風を循環させることで、エアコンの少なくて済む家に。


こんな風に、1Fから2F、2Fから3Fで色を変えるのもアリ。飽きの来ない変化のある空間に。




ナチュラル色の爽やかな階段。アンティークな照明が付いて家全体にレトロモダンがテーマとなっています。



建築面積7坪の狭小住宅。全く狭さを感じさせない階段です。窓からの光が、なんと明るい!階段上部が、隣の居室に抜けていて吹き抜けのようになっていることで、よりいっそう広がりを感じさせます。白とダークブラウンのコントラストで高級感のあるデザインに。


リビングダイニングからつながる階段。蹴込み板が白になっていて、ブラウンとの切り替えが、清潔感があって綺麗。ただの移動用空間ではない、ゆったりしたくつろぎの空間となっています。




和モダンの家に馴染みの良い、ナチュラルブラウンの自然な階段。こちらも採光通風の小窓がついて、快適な空間です。ムードのある温かい色の照明。



外の見える大きめの窓が付いています。朝起きたら、外の天気を確認しながら階段を降りて、食事へと家族が集まります。階段を上がったところには、収納が付いていて、便利。



建築面積たった6坪の狭小住宅の階段。少し幅の狭い階段ですが、開閉できる小窓が2箇所付いて、明るく、換気も出来て、自然で温かい空間になっています。
住宅デザイン特集
各施工事例の「玄関」を一挙紹介します。




扉を開けると、可動棚がたくさんあり、たった7坪の狭小住宅でも大容量収納を実現しています!白を基調に、スタイリッシュにまとめました。





階段下のほんのわずかなスペースも無駄にせず収納に。洗濯機置きのある扉付きの収納も玄関から続く廊下スペースに設けました。洗濯機置きは2Fにもあり、親世帯と子世帯で独立して洗濯機を使えます。玄関扉のガラスとシューズボックス上の小窓で採光通風を確保。


シックな色調の美しい玄関。もちろん可動棚で、棚の間隔は変えられます。こちらも玄関扉のガラスとシューズボックス上の小窓で明るく風通しの良い玄関を実現しました。



逆に究極のミニマルを追求した狭小住宅の玄関。シューズボックスも何もありません。ガラス扉の向こうはガレージ。


スペースに合わせて両サイドに分かれた収納棚。ナチュラルな木目調。





ゆったりした空間の玄関。お気に入りの鏡を吊るしています。玄関から続く廊下も収納が連なっています。




玄関を上がってすぐのところに大容量のウォークインクローゼット。これは便利!
営業設計・林のブログ
こどもエコすまい支援事業が9月に終了し、新たな住宅の省エネ支援事業が閣議決定されました。 (令和5年度補正予算2100億円)★国会での補正予算成立が前提ですが
【住宅の新築】18歳未満のお子様いる世帯又は、ご夫婦何れかが39歳以下の世帯で、
①長期優良住宅100万円/戸②ZEH住宅80万円/戸(※土砂災害警戒区域・浸水想定区域など除く)
【住宅のリフォーム】
①リフォーム省エネ改修②省エネ改修を前提に、バリアフリー改修・空気清浄機換気機能付エアコンの設置等について
子育て世帯、若年者世帯へ上限30万円/戸:その他の世帯へ上限20万円/戸
子育て世帯、若年者夫婦世帯が既存住宅を購入する場合に上限60万円/戸
長期優良住宅への改修で子育て世帯、若年者世帯に上限45万円/戸:その他の世帯で上限30万円/戸
こどもエコすまい支援と今回の制度の空白期間に契約着工してしまった方へ
今回の制度が閣議決定された11月2日以降、基礎工事以降の工程に着手するものは今回の新制度が利用出来、
11月1日の段階で上棟がされている物件は対象外になります。
独り言・・
業者・物件の登録に手間が掛かりすぎ、若年者世帯・子育て世帯の縛りは要らない、長期優良住宅は1フロアーが40㎡以上(階段室除く)の面積指定があり都内狭小住宅ではそもそも長期優良住宅が出来ない、身近なリフォーム補助が意外と少ない、そもそもその他の世帯(高齢者・単身世帯が置き去り・・・)と不満もあります。しかし、対象外になっても、これ以外の地域補助金、東京ゼロエミ、省エネ・耐震・建替え・リフォーム・太陽光・感震ブレーカー等活用して、無理無駄の無い家づくり・リフォームを行いましょう!
【家づくりの現場から】
大田区萩中では、耐震等級3の2階建て住宅(ガルバリウム鋼板仕様)、大田区大森東では、こどもエコすまい支援を利用したZEH仕様の3階建ての家が工事中です。断熱等性能等級6の基準+耐震等級3+制震住宅仕様での家づくり。(担当:林)
この後も、大森南・大森東・仲六郷と家づくりが続きます!ありがとうございます。

ビルトイン車庫+屋上付でも耐震等級3を取得しています。

ウレタン断熱で断熱・気密・遮音性を確保出来ます。


































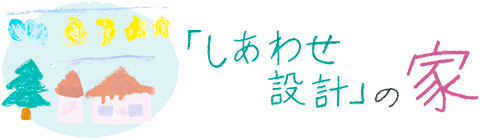
 ご相談
ご相談





















